並行的な政治経済的軌跡を描いてきた日独。しかし90年代に入り日本は「孤立」に、ドイツは「統合」の方向に向かい始めた。この現象に底流するものは何か。経済秩序のかたち、各国との相互依存関係、企業システムの違い等、両国の社会経済を多角的に比較する上で、米国的「グローバル資本主義」に対抗し得る地域経済の在り方を模索する意欲作。
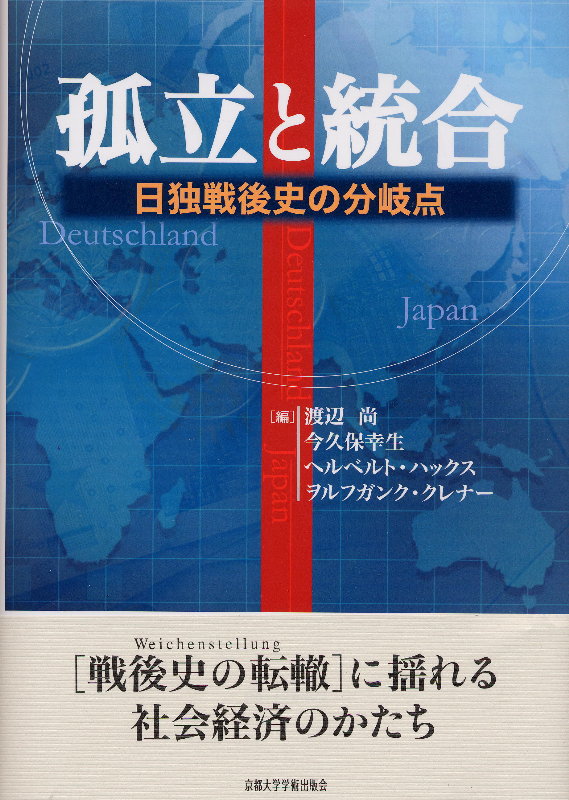
渡辺尚 序論
第1章 渡辺尚 「日本の危機状況と危機意識」
第2章 アルトゥール・ボル(渡辺尚訳)「ドイツ社会的市場経済の試練」
第3章 劉 進慶「日本型資本主義の新しいかたち」
第4章 ヲルフガンク・クレナー(黒澤隆文訳)「ドイツからみた日本型秩序論争」
第5章 竹内常善「日本の企業集団に見る連続と断絶」
第6章 .ヘルベルト・ハックス(石井聡・竹内常善・黒澤隆文 共訳)「市場変動とドイツの企業構造」
第7章 八林 秀一「対独関係から見た日本の貿易構造」
第8章 ギュンター・ハイドゥク,クリスティアン・シャッベル(八林秀一訳)「ドイツからみた独日経済関係の展望」
第9章 イェルク・ティーメ (黒澤隆文訳)「ドイツの対外経済関係とEU」
補論 「日本の対外経済関係 対米関係を中心に」
第10章 今久保幸生 「東アジア統合と日本の戦略」
第11章 ウィム・ケスタース,マルティン・ヘブラー(今久保幸生訳)「EU東方拡大とドイツ」
* * * *
総括と展望 渡辺尚
あとがき 今久保幸生
| 頁 | 行目 |
|
|
| 24 | 下2 | 「(米国のように | (米国のように |
| 53 | 注60 | 塩野谷裕一 | 塩野谷祐一 |
| 86 | 上6 | 企業的横断的な組織 | 企業横断的な組織 |
| 102 | 上16 | 金融機関と金融機関の間の | 金融機関とグループ内企業の間の |
| 109 | 上2 | それが置かれれた | それが置かれた |
| 132 | 下2 | やっと36位である | やっと34位である |
| 168 | 下12 | また.(句点)より規制が | また,(読点)より規制が |
| 188 | 下3 | 1900年の値 | 1999年の値 |
| 190 | 表5注 | マルタ、ポーランド | マルタ、ハンガリー、ポーランド |
| 217 | 下13 | 強調行動 | 協調行動 |
| 247-251 | 図4出典から図7出典まで | Sechverstandigenrat | Sachverstaendigenrat |
| 260 | 注2) 上4 | 欧州中欧銀行 | 欧州中央銀行 |
| 265 | 上6 | ブリキ版 | ブリキ板 |
| 265 | 上17 | ゼネラルエレクトリックス | ゼネラルエレクトリック |
| 268 | 上9 | 回を数える | 多数に及んだ |
| 269 | 下7 | (新日鉄社長)稲山嘉寛 | 稲山嘉寛(新日鉄社長) |
| 294 | 下12 | 日中とともに | 日韓とともに |
| 308 | 下5 | 1997年の | 1977年の |
| 309 | 上17 | ASEANと日中 | ASEANと日中韓 |
| 313 | 上18 | ASEAN+日韓両国に | ASEAN+中韓両国に |
| 318 | 下1 | 目本経済 | 日本経済 |
| 337 | 下1 | 2007年 | 2005年 |
| 345 | 上4 | (2003)通商白書 | (2003)『通商白書』 |
| 345 | 下4 | 世紀末アメカの | 世紀末アメリカの |
| 345 | 下10 | 家の光教会 | 家の光協会 |
| 347 | 上2 | 原洋之助 | 原洋之介 |
| 357 | 表3ITの行,比率の列 | 9.2 | 11.5 |
| 357 | 表3 SPの行以下,「比率」の項目の各行 | IRLの行まで,それぞれ数字一段ずつ繰り下げ | |
| 363 | 上11 | 1998年まの | 1998年までの |
