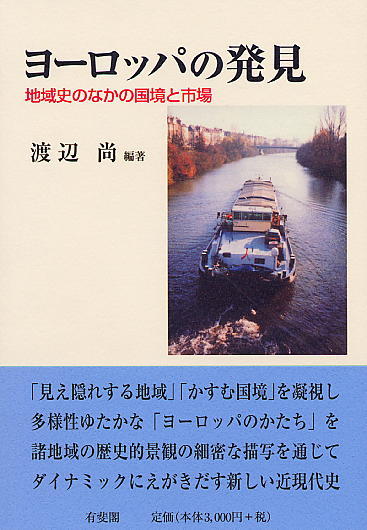| 氏名 | 所属等 | 主な研究テーマ |
| 井上直子 | 東京大学大学院 | |
| 今久保幸生 | 京都大学大学院経済学研究科 |
日本の東アジア統合政策に関する研究 ドイツ・ワイマル体制の通商政策に関する研究 |
| 尾崎 麻弥子 | 早稲田大学経済学研究科 | ジュネーヴを中心としたスイスのフランス語圏と現在のオート=サヴォワ県を中心としたフランスのスイス隣接地域との経済関係(移民、時計産業の分業) |
| 河﨑信樹 | 日本学術振興会特別研究員 | 第二次世界大戦後におけるアメリカ合衆国経済史及び対外政策史 |
| 黒澤隆文 | 京都大学大学院経済学研究科 | 近代スイス経済史,ヨーロッパ経済と経済政策、現代工業の諸問題 |
| 幸田亮一 | 熊本学園大学商学部 | 近現代ドイツ経営史,工業史 |
| 小島健 | 立正大学経済学部 | 欧州統合史,現代ベルギー経済史・経営史 |
| 佐藤勝則 | 東北大学大学院文学研究科歴史科学専攻ヨーロッパ史学 | 「中欧」統合史,ハプスブルク・ヨーロッパ史 |
| 高田茂臣 | 大東文化大学経営学部 | 近代ハプスブルク経済・経営史 |
| 長井栄二 | 秋田工業高等専門学校人文科学系 | 近代プロイセン政策過程・地域政策史 |
| 箱山健一 | 茨城工業高等専門学校 人文科学科 | ドイツ近現代史 農業経済論 特殊信用論 |
| 星隆介 | 東北大学大学院文学研究科 | 近現代ドイツ社会福祉政策史 |
| 森良次 | 福島大学経済学部 | 近代ドイツ経済史、ドイツ・ヨーロッパの産業・技術政策 |
| 渡邉尚 | 東京経済大学経済学部 | エウレギオ、ライン河運、ヨーロッパ地域政策 |
「国境を挟む協力:イタリア・スロヴェニア国境の町ゴリツィアの事例」、『ヨーロッパ統合と国際関係』、日本経済評論社、2005年所収。
【著書】
『孤立と統合 日独戦後史の分岐点』京都大学学術出版会[2006](渡辺尚,ヲルフガンク・クレナー、ヘルベルト・ハックスとの共編著。執筆担当:第10章・ 東アジア統合と日本の戦略(283-347頁)、第11章・EU東方拡大とドイツの訳者追記・訳注(371-380頁)、第3部序文(175-179頁)、第4部序文(279-281頁)、あとがき(389-392頁)
【論文】
3.「東アジア経済統合における日韓FTAの意義と課題」 2004年慶北大・京都大国際学術大会 『東北アジア経済協力の展望と課題』 慶北大学校経済通商学部(韓国),2004.12,発表3: 1-19頁所収
2. Auswirkungen von Globalisierungsprozessen und Krisenerscheinungen Ost- und Suedostasiens auf Konkurrenz- und Kooperationsbeziehungen in Asien----Eine Fallstudie der japanischen und ostasiatischen Elektronikindustrie---, in: Kyoto University Economic Review, Vol.72, No.1, 2003, S.1-22.
1. Effects of Globalization and Crisis
upon Competitive and Cooperative Relationships in Asia: The Example
of the Japanese and East Asian Electronics Industries", in:
Wolfgang Klenner and Hisashi Watanabe(eds.), Globalization and
Regional Dynamics. East Asia and the European Union from the Japanese
and the German Perspective, Springer 2002, S.81-107.
【ワーキングペーパー】
1. Integrationsmoeglichkeiten und -massnahmen Japans im ostasiatischen Raum, Working Paper No. 65, Graduate School of Economics/Faculty of Economics, Kyoto University, Januar 2003, S.1-29.
【翻訳】
1.ウィム・ケスタース、マルティン・ヘブラー著「EU東方拡大とドイツ」,今久保他共編著『孤立と統合 日独戦後史の分岐点』京都大学学術出版会 [2006],349-377, 380-383頁所収。
【書評】
3. 田野慶子著『ドイツ資本主義とエネルギー産業 工業化過程における石炭業・電力業』東京大学出版会 2003、『青山経済論集』第58巻第4号、2007.3、175-182頁所収
2. 田野慶子同上著、「ドイツ資本主義研究会(第二次)会報)、Nr.30、2004.11、4頁所収
1. 雨宮昭彦著『帝政期ドイツの新中間層-資本主義と階層形成-』東京大学出版会 2000年、『歴史と経済』【レフリー付学術誌】 第178号 XLV-2、2003.1、64-66頁所収
【教科書項目】
1. 「『電気の時代』をつくる」(単著)、経営史学会編・湯沢威編集代表『外国経営史の基礎知識』有斐閣、2005.2、284-285頁所収
【その他の報告書等】
2.「第5回 慶北大 - 京都大 国際学術大会について」(北野尚宏、村瀬哲司、菊谷達弥の報告要旨部分は各人の執筆による)『京大上海センターニュースレター』第59号(京都大学経済学研究科上海センタ)、153-156頁所収、2005.5.31
1. 第16回学会賞審査講評(山下充著『工作機械産業の職場史1889-1945』(早稲田大学出版部
2002、前田裕子著『戦時期航空機工業と生産技術形成』東京大学出版会 2001)『さんぱく』(日本産業技術史学会会報)第43号、2003年9月12~14頁所収
1.「第二次世界大戦後におけるアメリカのドイツ政策の史的展開~マーシャルプラン創出の背景をめぐって」(2001年度京都大学博士学位請求論文)
10.「マーシャルプランとハリマン委員会の設立」『経済論叢』(京都大学経済学会),第178巻第5/6号、2006年11/12月,112-128頁。
9.「H・モーゲンソー(Henry Morgenthau Jr.)とアメリカのドイツ占領政策構想~ルール地域をめぐる問題を中心に~」『アメリカ経済史研究』第3号、2004年9月
8.「占領下ドイツにおけるアメリカ石油企業の事業再構築活動に対するアメリカ政府の対応~ソコニー・バキューム社(Socony Vacuum Oil Company)の事例を中心に~」(京都大学『経済論叢』第174巻第3号、2004年9月
7.「H・L・スティムソン(H・L・Stimson)とアメリカのドイツ占領政策構想~モーゲンソープランへの批判(1944年8月~10月)を中心として~」京都大学『調査と研究』第28号、2004年4月
6.「占領期におけるアメリカ企業のドイツ企業買収に対するアメリカ国務省の対応~スタンダード・オイル社によるロイヤル・ダッチ・シェル社との共同買収の事例を中心に~」京都大学『経済論叢』第173巻第2号、2004年2月
5.「マーシャルプラン再考~「コーポラティズム論」との関連を中心として~」(京都大学『経済論叢』2002年5・6月号掲載)
4.「ヨーロッパ決済同盟成立以前における西ドイツ貿易とマーシャルプラン」(京都大学『調査と研究』2001年10月号)
3.「H・フーバー(Herbert Hoover)のドイツ報告(1947年3月18日)とその歴史的位置」(京都大学『経済論叢』2001年2月号)
2.「1949年ドイツマルク切り下げ問題をめぐる米仏関係」(京都大学『経済論叢』2000年10月号)
1.「J・F・ダレス(John Foster Dulles)とアメリカのドイツ経済復興政策-超党派外交とマーシャルプランの起源に関する一考察」(『史林』83巻4号、2000年7月)
1.「書評:渡辺尚編著『ヨーロッパの発見 地域史の中の国境と市場』(有斐閣、2000年)」(福島大学『商学論叢』第70巻1号、菅原歩 氏、村山弘氏、高田茂臣氏、橋口勝利氏、森良次氏との共著)
4.「アメリカのドイツ政策をめぐる外交問題評議会の活動--ドイツ問題研究会(1946~47年の分析を中心として)」(社会経済史学会第72回全国大会、自由論題報告 東京経済大学[2003年6月1日])
3.「アメリカ企業の在ドイツ子会社に対する投資禁止政策と「冷戦」」(社会経済史学会第70回全国大会、自由論題報告、上智大学(2001年5月19日)
2.「マーシャルプラン期におけるアメリカの対ドイツ投資禁止政策の変容~アメリカ石油産業の対ドイツ投資の事例を中心に」(社会経済史学会近畿部会11月例会、神戸学院大学(2000年11月18日)
1.「マーシャルプランにいたるアメリカのドイツ経済復興政策」(社会経済史学会第68回 全国大会、自由論題報告、京都大学(1999年5月29日))
9.「スイスの工業化過程における商人と商業・金融業 (第72回〔社会経済史学会〕全国大会共通論題)」『社会経済史学』 第70巻4号,2004年11月,417-436頁。
8(b).Kurosawa Takafumi, (Uebersetzung: Kurosawa Takafumi und Harald Meyer),“Das Image der Schweizer Wirtschaft in Japan: Wirtschaftspolitische Selbstbildnisse in Zuge eines Modernisierungsprozesses”, in: Asiatische Studien. Zeitschrift der Schweizerischen Asiengesellschaft. 2004. S.45-67.
8(a)「日本におけるスイス経済像――その変容にみる近代像・経済政策認識の変遷」,森田安一(編)『スイスと日本――日本におけるスイス受容の諸相』刀水書房書房,2004年[平成16年)10月,159-186頁。
7.「スイス」財務省財務総合政策研究所 「経済の発展・衰退・再生に関する研究会」報告書第6章 2001年6月 139-165頁
6.アルプスの孤高の小国 スイス」渡辺尚編著『ヨーロッパの発見 地域史のなかの国家と市場』有斐閣 2000年 163-220ページ所収。ISBN4-641-07636-7
5.スイス鉄道網の形成過程――19世紀の鉄道政策と経済空間」森田安一編『スイスの歴史と文化』刀水書房 1999年 所収 ISBN 4-88708-235-5
4.「スイス統一関税圏の成立過程と19世紀スイスの自由貿易主義(2)」『調査と研究』(京都大学『経済論叢』別冊)第15号(1998年4月号)18-42ページ
3.「スイス統一関税圏の成立過程と19世紀スイスの自由貿易主義(1)」『調査と研究』(京都大学『経済論叢』別冊)第14号(1997年10月号)66-80ページ。
2.「19世紀東スイス・フォアアールベルクの農村工業と世界市場」『調査と研究』(京都大学『経済論叢』別冊)第11号(1996年10月号)88-107ページ。
1.「高ライン地域の国境間経済関係──産業革命期の綿工業を中心に──」『社会経済史学』第62巻第4号 (1996年10・11月号)1-30ページ。
3.「スイス連邦制の歴史と現状[研究会報告(2006年2月13日)]」佐藤勝則『比較連邦制史の研究 科学研究費研究成果報告書』2006年,86-95頁
2. 「上海・武漢訪問記 ---「国際交流科目」と3つの工場見学」京都大学上海センター ニュースレター 第108号(2006年5月10日/第109号(同5月17日)掲載記事
1. (渡辺尚と共著)<コンファレンス・レポート>「第68回全国大会共通論題『地域統合の歴史的諸形態』」『社会経済史学』67-2
2001年7月,83-93ページ。
3.ヲルフガンク・クレナー著「ドイツから見た日本型秩序論争」,渡辺尚,今久保幸生,ヘルベルト・ハックス,『孤立と統合 日独戦後史の分岐点』京都大学学術出版会,2006年3月,ISBN4-87698-679-7,99-122頁所収。ヘルベルト・ハックス「市場変動とドイツの企業構造」(石井聡・竹内常善と共訳),同書151-179頁所収,イェルク・ティーメ著「ドイツの対外経済関係とEU」,同書241-262頁所収。
2.ヘルベルト・ハックス著「日独における経済政策的優先課題としての成長と雇用」渡辺尚・W.クレナー編『型の試練──構造変化と日独経済』所収 信山社 1998年 ISBN 4-7972-2108-9 [13-24頁所収]
1.森田安一監訳 U.イム・ホーフ著『スイスの歴史』刀水書房 1997年
ISBN 4-88708-207-X (共訳/第8章[173-206頁]のみを担当)
6. "Akira Kudo/Matthias Kipping/ Harm G. Schroeter (ed,), German and Japanese Business in the Boom Years. Transforming American management and technology models", in: Zeitschrift fuer Unternehmensgeschichte/ Journal of Business History. Nr.2/2006, 51. Jahrgang, 255-257
5. 「ポール・ギショネ著(内田日出海・尾崎麻弥子訳『フランス・スイス国境の政治経済史---越境,中立,フリー・ゾーン』」『社会経済史学』第72巻第2号,2006年7月,117-119頁。
4.「篠塚信義・石坂昭雄・高橋秀行編著 地域工業化の比較史的研究」『社会経済史学』第70巻第2号,2004年,249~251頁所収。
3.「松原宏[編]『先進国経済の地域構造』」『歴史と経済(旧 土地制度史學)』第182号,2004年1月,55-58頁所収。
2.「岩井隆夫[著]『近世スイス農村市場と国家』」『社会経済史学』Vol.69, No. 4, 2003年11月,115-117頁所収。
1.「デレック・H・オルドクロフト著,玉木俊明・塩谷昌史訳『20世紀のヨーロッパ経済--1914~2000年』」『比較経済体制研究』第10号,2003年7月,147-152頁所収
[教科書など]
1.「総論:ドイツとヨーロッパ諸国」/「鉄道のインパクト--19世紀ドイツ語圏」/「<ドイツ・モデル>と<ライン資本主義>」[いずれも大阪大学ばん澤歩助教授と共著]/「知られざる先進工業国スイスの企業」[単著],経営史学会編・湯沢威編集代表『外国経営史の基礎知識』有斐閣,2005年。
9. 「VDF旋盤の誕生 -ドイツ合理化運動のシンボル」『熊本学園商学論集』第13巻第2号 (20061200) pp. 1-17.
8.「熊本における『産業革命』と産業遺産の可能性-旧熊本紡績赤れんが工場の熊本学園大学への移築に際して-」『熊本学園大学産業経営研究』第23号(2004年3月)(1-12頁)
7. Ryoichi Koda, Technological Innovation in Japan: A Comparison of Japanese NC-Machine Tool Development with the Western Process, in: Karl R. Kegler & Max Kerner (Hrsg.), Technik Welt Kultur - Techinische Zivilisation und Kulturelle Identitaen im Zeitalter der Globalisierung, Koeln: Bohlau Verlag 2003. (S.141-161)
6.「1930年代のドイツ工作機械工業」『熊本学園商学論集』第8巻第2号、2001年12月.
5.「両大戦間期ドイツにおける工作機械工業の地域構造」『経済論叢』第173巻第3号、2001年3月.
4.「金属・機械工業の集積と課題」『熊本県産業経済の推移と展望-自立と連携をめざす地域社会』(熊本学園大学産業経営研究所編)日本評論社、2001年、所収.
3.「中央ヨーロッパの企業発展」『現代ヨーロッパ経営史』(渡辺尚・作道潤編)、有斐閣,1996年、所収
2.『ドイツ工作機械工業成立史』多賀出版,1994年.
1."Technologietransfer von Deutschland nach Japan im Rahmen der Werkzeugmaschinenindustrie vor dem Zweiten Weltkrieg" in: Technologietransfer Deutschland - Japan von 1850 bis zur Gegenwart(Hrsg. Erich Pauer), Muenchen 1992.
14.【単著・著書】『欧州建設とベルギー』日本経済評論社,2007年
13.「EEC設立におけるベネルクス経済同盟の役割」,立正大学『経済学季報』第56巻第3・4号, 2007年3月
12.「戦間期における欧州統合構想」,立正大学『経済学季報』第56巻第1・2号,2006年12月
11.「ベルギー新自由主義の軌跡」,権上康男編著『新自由主義と戦後資本主義』日本経済評論社,2006年
10.「『小国』ベルギーの経験-欧州統合と地方分権の同時進行」,『NIRA政策研究-欧州統合の歴史と現在-』2001年12月号,総合研究開発機構。
9.「ヨーロッパ統合の中核-ベネルクス経済同盟-」渡辺尚編『ヨーロッパの発見-地域史のなかの国境と市場』有斐閣,2000年,第2章。
8.「ベルギー・ルクセンブルク経済同盟の設立と展開」,『経済学季報』(立正大学経済学会)第49巻第2号,1999年10月。
7.「ベルギーの戦後再建と欧州統合-石炭業を中心に-」,『経済学季報』(立正大学経済学会)第47巻第3・4合併号,1998年3月。
6.「ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体とベルギー石炭業」,廣田功・森建資編著『戦後再建期のヨーロッパ経済-復興から統合へ-』日本経済評論社,1998年,第6章。
5.「ヨーロッパ統合と企業発展」,渡辺尚・作道潤編『現代ヨーロッパ経営史』有斐閣,1996年,第7章。
4.「1950年代前半西ヨーロッパにおける共同市場構想-ヨーロッパ政治共同体設立計画を中心に-」,『修道商学』(広島修道大学商経学会),第35巻第2号,1995年3月
3.「国際工業カルテルと国際連盟」,藤瀬浩司編『世界大不況と国際連盟』名古屋大学出版会,1994年,第6章。
2.「ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体の誕生-ベルギーの対応を中心として-」『土地制度史学』第134号,1992年1月。
1.「設立期におけるEECの低開発国政策-植民地支配から連合関係への転換を中心にして-」,『経済科学』(名古屋大学経済学会),第36巻第1号,1988年7月。
2.『南チロルの旅』共同印刷、2007年3月
1『オーストリア農民解放史研究-東中欧地域社会史研究序説-』多賀出版 1992年
18.「連邦制と基礎自治体-平成の市町村合併の世界史的位置-」『比較連邦制史の研究2006-科学研究費研究成果報告書-』共同印刷、2007年3月。
17.「「連邦制ヨーロッパ」の世界史的位置-問題把握の基礎視点- 」『比較連邦史の研究2005-調査と基礎資料-』共同印刷、2006年3月。
16.「「古いヨーロッパ」のアイデンティテー-オーストリア史の歴史的射程から-」 『ヨー ロッパ研究』第5号、2005年12月。
15.「19世紀末オーストリアにおける都市建設と不動産抵当証券―ウィーン取引所史を手がかりに―」『文化』第68巻3・4号 2005年
14.「連邦制ヨーロッパの郷土意識―ヨハン大公と近現代オーストリア―」『史潮』第56号 2004年
13.「三月革命期のオーストリアにおける地方等族議会改革―シュテンデ中央委員会関連文書の分析を中心に―」『文化』第66巻第1・2号 2002年
12.「統合ヨーロッパの一源流―ハプスブルク帝国―」渡辺尚編著『ヨーロッパの発見』有斐閣 2000年
11.「オーストリアの連邦制と地域社会」『地域史から見たヨーロッパ』共同印刷 1998年
10.「オーストリア千年と地域史研究」『歴史』第89号 1997年
9.「オーストリア農民解放史研究再考―地域社会史研究の方法的可能性―」『西洋史研究』新輯第23号 1994年
8.「三月前期西南ドイツ・リストの財政改革論―租税連合=連邦制国家を展望して―」『文化』第58巻第1・2号 1994年
7.「三月前期西南ドイツ・リストの市民社会論―シュテンデ改革論から農地制度論ヘ―」 欧米近現代史研究会編『西洋近代における国家と社会』共同出版 1994年
6.「ヨーロッパ地域社会史研究の一視角―近代市民社会と地方自治―」『西洋史研究』新輯第21号 1992年
5.「オーストリア・ハンガリー関税・貿易政策と対外決済危機―シュンペーター帝国主義論の現実的基盤をめぐって―」桑原・井上・伊藤編著『イギリス資本主義と帝国主義世界』九州大学出版会 1990年
4.「オーストリア・ハンガリー二重帝国統治体制に関する一考察―特にアウスグライヒ=二重主義体制の推転に即して―」『西洋史研究』新輯第18号 1989年
3.「オーストリア・ハンガリー中央銀行政策と世界市場―金本位制下の再生産=信用構造把握のために―」藤瀬浩司・吉岡昭彦編著『国際金本位制と中央銀行政策』名古 屋大学出版会 1987年
2.「オーストリア立憲帝国議会宛請願書目録分析―1848年革命における変革課題把握のために―」『西洋史研究』新輯第12号 1983年
1.「リストの政治経済学とコッシュートの立場―三月前期におけるドイツの国民的利害とハンガリー―」『茨城大学政経学会雑誌』第46号 1982年
1.ベレンド・ラーンキ著『東欧経済史』中央大学出版会(南塚信吾監訳)1978年
1.『ハプスブルク帝国紀行―多元的地域主義の歴史的源流―』共同印刷 2002年
(Discussion Paper)
・「戦間期中国における米系国際銀行-International Banking Corporation 北京支店、天津支 店、広東支店」Discussion
Paper, Tohoku Management & Accounting Reseach Group、no. 78、2007年3月、pp.1-19.
[博士論文]
・「19世紀ハンガリーの産業革命-ハンガリー資本主義像の再検討-」京都大学大学院経済学研究科博士論文,2007年。
【論文・学会報告】
9.「ガンツ鋳鉄・機械工場の電機事業戦略―『第二次産業革命』とハンガリー工業企業―」『経営史学』第41巻第1号,2006年6月
8.「19世紀ハンガリーにおける革新的企業家活動―ガンツ鋳鉄・機械工場の創業と発展の事例に即して―」『企業家研究』第3号,2006年6月
7.「ブダペシュト製粉業における工場制度の確立―近代技術の導入と資本-賃労働関係の 成立を中心に―」『社会経済史学』第71巻第6号,2006年3月
6.「ガンツ鋳鉄・機械工場の経営発展と技術者的企業家(1844年~1870年代末)」社会経済史学会第71回全国大会自由論題報告、和歌山大学、2002年5月18日。
5.「ガンツ鋳鉄・機械工場の創業と発展―ハンガリー産業革命と国際企業家活動―」経営史学会関西部会12月例会報告、同志社大学、2001年12月15日。
4.「書評 渡辺尚編著『ヨーロッパの発見 地域史の中の国境と市場』(有斐閣、2000年)」(森良次/橋口勝利/村山弘/河崎信樹/菅原歩との共著)、『福島大学商学論
集』第70巻第1号、2001年10月。
3.「ハンガリー産業革命の特質―主導的産業としての機械製粉業を中心に―」土地制度史学会秋季学術大会自由論題報告、岩手大学、2001年10月13日。
2.「ブダペシュト地域の工業化と製粉業・機械産業の成立過程―産業革命のハンガリー的特質を巡って―」社会経済史学会近畿部会4月例会報告、神戸大学、2001年4月21
日。
1.「二重帝国期・ハンガリー王国の製粉業と地域-ハンガリー産業革命研究序説」、
1999年度京都大学修士論文。
【書評】
2. 「<書評>薩摩秀登著『物語 チェコの歴史』(中公新書,2006年)」『比較経済体制研究』第13号,2006年12月。
1. (森良次・橋口勝利・村山弘・河崎信樹・菅原歩と共著)「<書評>渡辺尚編著『ヨーロッパの発見 地域史の中の国境と市場』(有斐閣,2000年)」『商学論集』第70巻第1号,2001年9月。
【教科書項目】
・「ハンガリー―農業国の工業企業」経営史学会編・湯沢威編集代表『外国経営史の基礎知識』有斐閣,2005 年
・「大不況期プロイセンにおける農村地域政策論の形成 ─── 社会政策学会論争(1882-90年)の分析 」学位論文, 1999年.
4.「『大不況』期プロイセンにおける農村地域政策論の形成(2)」『秋田工業高等専門学校研究紀要』第42号、2007年2月、66-73頁。
3.「『大不況』期プロイセンにおける農村地域政策論の形成(1)」『秋田工業高等専門学校研究紀要』第41号、2006年2月、63-70頁。
2.「大不況期プロイセンにおける農村地方制度改革構想の形成─── 1890年社会政策学会大会討論と現状報告者提言の分析」 『歴史』第90輯, 1998年, 所収.
1.「第二帝制期プロイセン東部における地方制度改革問題とゲマインデ自治─── 1890年社会政策学会報告の分析」 『西洋史研究』新輯第25号, 1996年, 所収
【書評】
1.「加藤房雄著『ドイツ都市近郊農村史研究-「都市史と農村史のあいだ」序説-』」『歴史』
第106輯、2006年4月、144-152頁。
3.2001年度土地制度史学会秋季学術大会自由論題報告(2001年10月13日, 岩手大学)「大不況期におけるプロイセン内地植民政策の形成過程」
2.1999年度西洋史研究会大会自由論題報告(1999年11月13日, 立教大学)「大不況期ドイツ社会政策学会における農村地域政策論の形成」
1.社会経済史学会第66回全国大会自由論題報告(1997年5月31日, 東北大学)「『新航路』期プロイセン東部農村における地方制度改革問題とゲマインデ自治」
3.「バイエルンの経済空間--農業国の産業革命」『茨城工業高等専門学校研究彙報』 (38) [2003.3] 1~8頁
2.「二十世紀初頭ニーダーバイエルンにおける農業物流・決済の組織化――ドナウ流域地方とバイエリッシャーバルト地方の比較から」『茨城工業高等専門学校研究彙報』 第37号(2002.3)1-8頁。
1.「ドイツ帝国主義における農業地域経済――「貸手」としての農業信用の成立」『茨城工業高等専門学校研究彙報』第36号(2001).1-8頁
1.「1920年代ドイツにおける社会保障制度と地方財政--失業給付問題を中心に--」『西洋史研究』新輯29,2000年
4.「前三月革命期バーデンの小営業政策と「社会問題」」『商学論集』(福島大学)第75巻1号(2006年10月)69-93 頁。
3.研究ノート 「19世紀ドイツ営業補習学校の発展とその地域的格差」『商学論集』(福島大学)第72巻第3号(2004年2月)67-78頁。
2.「ヴュルテンベルクにおける編物産業の発展とその背景」『経済論叢別冊 調査と研究』(京都大学)第21号(2001年4月) 82-96頁。
1.「19世紀後半西南ドイツ・ヴュルテンベルクの産業振興政策」『経済論叢別冊 調査と研究』(京都大学)第16号(1998年10月)
[書評]
(森 良次 ; 高田 茂臣 ; 橋口 勝利 他) 「渡辺尚編著「ヨーロッパの発見 地域史の中の国境と市場」『商学論集』(福島大学経済学会) 70(1) [2001.10],85-102頁。
8.渡辺尚,今久保幸生,ヘルベルト・ハックス,ヲルフガンク・クレナー(編)『孤立と統合 日独戦後史の分岐点』京都大学学術出版会2006年3月
7.Wolfgang Klenner/ Hisashi Watanabe(Editors), "Globalization and Regional Dynamics: East Asia and the European Union from the Japanese and the German Perspective", Springer,20021
6.『ヨーロッパの発見―地域史のなかの国境と市場―』有斐閣、平成12年(編著)
5.『型の試練―構造変化と日独経済―』信山社、平成10年
4.『現代ヨーロッパ経営史―「地域」の視点から―』有斐閣、平成8年(共編)
3.『ドイツ経済の歴史的空間―関税同盟・ライヒ・ブント―』昭和堂、平成6年(共著)
2.『シンポジウム・日本とドイツの外国人労働者』明石書店、平成3年(共編)
1..『ラインの産業革命―原経済圏の形成過程―』東洋経済新報社、昭和62年(単著)
9.「一西洋経済史家の戦後六十年」『福大史学』78・79合併号、2006年3月 (2007年2月刊行)
8.「ファブリカントとカオフマン-産業革命期ニーダーラインの商人たち-」 『追手門経済論集』第41巻、第1号、2006年11月
7.「「地域のヨーロッパ」の再検討(2)-ドイツ・ネーデルラント国境地域に 即して-」『東京経大学会誌』251号、2006年10月
6.「EUの内部国境-ドイツ・オランダ国境地域に即して-」『東京経済大学 学術研究センター年報』2005年度、第6号、2006年8月
5..「地域のヨーロッパ」の再検討(1)--ドイツ・ネーデルラント国境地域に即して」『東京経大学会誌』247号,2005年11月,21-40頁。
4..Euregios und Urwirtschaftsraume―Fuhrt die Relativierung der Staatsgrenzen Europas zur Gestaltung neuer Wirtschaftsraume? in: Jurgen Schneider(Hrsg.), Naturliche und politische Grenzen als soziale und wirtschaftliche Herausforderung:Referate der 19. Arbeitstagung der Gesellschaft fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 18. bis 20. April 2001 in Aachen(VSWG-Beiheft 166), Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2003, pp.269~299.
3.「近代ヨーロッパにおける海と陸との変容」川勝平太・濱下武志編『海と資本主義』東洋経済新報社、2003年7月、67~98頁。
2.「エウレギオとEU国境地域政策」『日本EU学会年報』第22号,2002年
1.「停年退官記念最終講義 未来への逃避,歴史への投企(2)社会科学的時間認識の諸問題」『経済論叢』京都大学経済学会 / 京都大学経済学会 〔編〕,168(1) [2001.7] ,1~19頁。
3.内田洋一著「風の天主堂」『熊本日日新聞』2008年6月1日掲載(下記画像は,書評著者の渡辺尚氏,ならびに『熊本日日新聞』の許諾をえて転載)
2..「原輝史編著『EU経営史』 」『経営史学』39(1) [2004] ,90~93頁。
1.「書評:山田徹雄著『ドイツ資本主義と鉄道』」『鉄道史学』第21号、2003年7月、89~91頁。
2.「どこへゆくのか?EU経済」東京経済大学国際経済グループ『私たちの国際経済-見つめよう、考えよう、世界のこと-』有斐閣、2003年9月、143~160頁(第8章)
1..(辻 悟一 ; 渡辺 尚; 石井 吉春)「座談会 欧州の地域政策に学ぶ (特集 欧州の地域政策に学ぶ) 『RPレビュー』日本政策投資銀行設備投資研究所地域政策研究センター / 日本政策投資銀行設備投資研究所地域政策研究センター 編 2001(2) (通号 5) [2001.7] ,4~12頁。
2..「国際経済学科開設記念 国際シンポジウム2002「日本の選択―経済グローバル化とアジアの地域協力」を終えて:二日目総括」『東京経済大学学報』第35巻第4号、2003年。
1. 「「地帯構造論」から「地域構造論」へ--『ヨーロッパの発見--地域史のなかの国境と市場』を編集して」『書斎の窓』有斐閣 (504) [2001.5] ,22~26頁。
研究会の活動成果ではないが,研究会発足の契機となった出版物で,研究会の問題関心を直接に反映した作品。